【経文】
無限界 乃至 無意識界
【読み方】
ムゲンカイ ナイシ ムイシキカイ
【現代語訳】
限界もなく 乃至 意識界もなし
* 感覚器官と対象領域との接触により生ずる六つの認識世界 (六界) のこと
合計十八界の全てがない
<解説> 今回のキーワード 「五十三の無」
「眼」 と 「色」 が縁じ合わなければ 「眼が色を見る」 こともなく
「耳」 と 「声」 が縁じ合わなければ 「耳が声を聞く」 こともない
16句~19句では 「小乗仏教の十八界」 などというものは
「空」 の中には無いのである
そのことを経文は 「無限界 乃至 無意識界」 というのである
さて いよいよ 「無」 の登場です
16句から23句までに 「無」 が十三文字出てくるが
「六根」 「六境」 各一字それぞれに 「無」 が繋がるから 実は 「五十三の無」 が
登場している
そして この場合の 「無」 は 先の 「空」 と同じ意味である
すなわち 「ない」 ということは 数字の 「ゼロ」 と同じことだと ここでは理解したい
すべてが「無」で「空」だと認識することからスタートして苦しみを克服すべきである
苦しみを克服するのには 「彼岸に渡る必要はない この娑婆で生活していていい
のだ」 と前回説明したが 確かにその通りなのであるが
この言葉は少々誤解される危険がある
実は 仏教が仏教である限り どうしても欠かせない基本原理がある
その基本原理は 「出世間」 である 即ち 世間を出る 世間を離れる 世間を捨てる
そうでないと仏教とはいえない
釈迦は王室を捨て (出家=家を出て) 悟りを開いた
ここで出家をホームレス化と解釈しては 小乗仏教的になる
そうではなく大乗仏教では 「世間の物差しを捨てる」 ことだという
全てのかかわりを一度は捨てろと言う
我々は世間の物差し ・ 価値観に縛られている 奴隷になっている
そんな物差しを捨てて そして自由になれ!というのが 「出世間」 である
例えば 子供は学校に行くべきだ 真面目な人間は会社に行くべきだ
というのが世間一般の物差し ・ 価値観である
もちろん その物差し ・ 価値観で悩まずに行動できる人はそれでいいのである
そういう人は別段それに縛られているわけではない
ところが その物差し ・ 価値観が重くのしかかってくる人がいる
最近はそういう人が特に多くなっている
そういう人は 物差し ・ 価値観を捨てなさい そして自由になりなさい
「般若心経」 はそう教えている
学校に行きたくなければ 行かなくていい 会社を休みたければ 欠勤すればいい
ところがきっと反論がある 馬鹿なこと言うな!
皆がまねすれば社会が崩壊するぞ!
だが そう反論する人は すでに社会の奴隷になっているのである
「般若心経」 は奴隷になるな!と教えている わたしたちは自由なのである
自分の幸福を護る権利は わたしたちにある
自由人は社会に縛られていない それが 「出世間」 である
学校に行きたくないと思うのは その子が体と心で何かを感じ取っているのであり
学校に行けば自分の人格が崩れてしまう
そんな危険信号を敏感にキャッチしている
それを 世間の奴隷は 「そう思うのはいけないことだ」 と無理やり 行こうとする
自分の体や心が発する信号を 世間の奴隷は
まるで悪魔の誘惑のごとくはねつける
だから 子供が自殺したり サラリーマンが過労死したりする
だが 「ずる休み=怠け」 を推奨するのではない 早合点してはいけない
怠けてはいけないと 意地になって思い込んでしまう この姿が奴隷であり
これが問題だというのである
六波羅蜜の中に 「精進」 という言葉があるが
一般には 「がんばる」 ことと理解されやすい
辞書で “がんばる” とはいかに書かれているか?
* 「頑張る」 とは 当て字で 「我を張る」「眼張る」 が転じたもので次の意味がある
① 他の意見を押しのけて強く自分の意見を押し通す
② ある場所に座を占めて少しも動こうとしない
③ 苦しさに負けずに努力する
上記の①&②は頑張らないで「少しずつ譲ればお互い楽になる」 と誰もが気付く
ところが③の意味は良いことだと考えて
誰もが 「がんばれ!」 「がんばります」 という
しかし仏教的には 「がんばるな!」 と捉えて欲しい
努力はするとしても 「ゆったり ・ 楽しい努力」 であってほしいというのである
どうして苦しさに負けるといけないのか?果たして弱者を見捨てて幸福だろうか?
そこに 「般若波羅蜜」 が必要とされ
世間の奴隷ではない 自由人の智慧 ・ 仏の智慧 ・ 世間の物差しに 縛られずに
自由に考えて自分の行動を律することの智慧が必要となる
最後に一言だけ付け加えておく
努力すれば幸福になると思うのは間違いである
本当は幸福だから努力できるのである
「精進」とは幸福な人がする努力であり 奴隷がする努力ではないということである
2006年11月17日
|
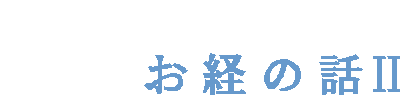
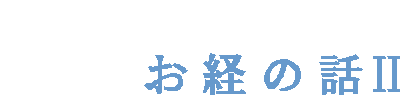
![]()